御来訪ありがとうございます。
 |
|
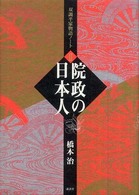
院政の日本人―双調平家物語ノート〈2〉
NHK大河ドラマは、「平清盛」 で、視聴率は良くないようでございます。
あのNHKが、理由もなく大河ドラマのテーマを選ぶはずはございません。
何で清盛?
最初は、神戸プッシュ(福原は神戸)かなあ? それとも、平家は源氏(清和源氏)に負けた。 自民党に清和会ってのがありますね。 その話だからかなあ。。 なんて思っていたのですが、上記の2冊を読んで、謎が解けました。
平清盛は、平家物語で、物凄い悪人として描かれています。ところが、双 調平家物語を書いていた橋本さんは、そんなに悪いことしたわけじゃない のに、どうしてこんなに悪く書かれるのか、疑問に思ったそうです。
それで、平家物語で、こんなに清盛が悪いイメージをつけられたのは、
清盛が、悪人だったからではなく、当時の摂関家の財産や、権限に手を つけようとした。つまり、官僚貴族の領分に踏み込んで一時的にでも上位 に上った。そのことが許せなくて、あんなに悪人に書かれたのだろう と いうのです。
つまり、宮廷官僚が勝者であり、平家は壇ノ浦で滅んだけれど、それ以 前に、清盛は当時の朝廷の官僚貴族に負けたのです。
しかも、官僚貴族らしい人事によってです。
想像して現代に置き換えてみますと、新しい世を作ろうとした武士(政治 家)が、官僚に負ける話なんですよ。 神戸プッシュとともに。。
NHKと官僚の自己満足モノなので、数字も取れないんでしょうね。(苦 笑)
【誠天調書】
2011年10月24
を読ませていただいたときも良くわからなかったことが、この2冊の本を読 んで少し繋がりました。
に、関連事項が少し出て来ますが、多分、今後何回も この本のことが出てくると思います。
日本の特徴的な二重権力の系譜は、持統天皇が、自分の孫に天皇の位を譲るために 上皇は天皇に準ずる と書いてしまったことある。
それ以前も似たような状態 葛城氏 蘇我氏 とありますが、律令にしてしまったのは持統天皇というわけです。
いくつか印象的で、今に通じそうなことをあげてみます。
日本の権力者は、「自分に合わせてルールを変えろ」とは言わず、 「自分達 だけに対して ルールを曲げろ」 と言う。
白河上皇は自分の愛した女御がなくなっても御所から返しませんでした。 当時は、御所でなくなる前に実家に帰したそうなのですが 「朕は、例外 にせよ」みたいなものです。
持統天皇は、跡継ぎの孫の世の安定を願って、律令を作りますが、 そ の皇太子を脅かしそうなまだ生存している王子を 律令の中にない官位 を作って、そのポストにつけて、「偉い人だけど、継承者じゃない。臣下で ある」 をアピールして 孫が正当な継承者であると認めさせることに成 功する。
藤原氏は、今まで皇后は皇族というルールを自分の都合で変える。
同じく、皇太子は男というルールを自分の都合で変える。
という風に、その時の権力者が、法というものを自分だけは別 と運用し てきたのです。
ですから、今の官僚が、法を都合よく運用するのは、古来の伝統なので すね。
摂関家は主権者のコントロールに全力を注ぐ
嵯峨天皇の未亡人である壇林皇后 橘 嘉智子は、娘の子どもを取るか
息子を取るかで、後ろ盾となる藤原氏がいる息子を選びます。
そこから、藤原氏の摂関家への道が始まります。
娘をもうけて、育て、天皇家に入内させ、男の子を生ませて次の天皇にす る。外舅として力を持つというシステムです。
持統天皇の時代には、天皇になる「資格」と「能力」がないと周囲を納得 させられなかった状態も、いつしか 資格(血統)と、能力(摂関家)に分離さ れていきます。
摂関家は内部では実力主義で、兄弟で競い合い、娘を育て上げ、入内さ せていきます。 また、意に沿わない天皇、皇太子は、騙したり、出仕しな い(サボタージュ)したりして、譲位に追い込んだり、帝位を辞退させたりし ています。そうやって、天皇は、住んでいる清涼殿から出るだけで「御幸」 と言われるくらい箱入りとなってしまうのです。
ライバルになりそうな相手が出てきた場合は、「呪詛した」と訴え出て
追い落とします。
今の官僚が、検察やマスコミを使って、追い落とすのとおんなじですね。
また、戦前の天皇主権のイメージをそのまま利用して、現在の主権者で ある国民をコントロールしています。女性宮家というのは、首都機能移転 や、皇室が関西に行った時のために、官僚の皇室とのつなぎ役という場 を増やすため、東京で権威を保つためのツールでもあるのでしょう。
道長の時代に 4人の娘を天皇 皇太子に入内させて、「欠けたることも なしと思へば」 という絶頂期を迎えますが、その後橋本さん曰く
「道長の過剰投資に苦しむ」ことになります。
4人の娘を入内させてしまったために、そこに男の子が生まれなくても、
道長の息子の頼道、教道は、姉の彰子が預かる皇女の入内を止めるこ とも、自分の娘を入内させることもできなくなります。
そして兄弟で、摂政にしろ、氏長者にしろ 娘を皇后にしろ と争い、そう こうしているうちに 摂関家の娘の子どもではない後三条天皇が生まれ てしまうのです。
荘園というのは税の私物化である。
班田収授法
墾田永年私財法
聖武天皇の治世に、天平15年5月27日(743年6月23日)に発布された勅(天皇の名による命令)で、墾田(自分で新しく開墾した耕地)の永年私財化を認める法令である。古くは墾田永世私有法と呼称した。荘園発生の基礎となった法令である。
土地を国有化してそれを分け与えて税を徴収するというのが律令制の根 本だったわけですが、人口が増えて開墾が追いつかないので 墾田永年 私財法 になっていく という説明を学校で受けたと思います。
橋本さんはこう書きます。
「これは、力のあるものが開墾をできるわけで、日本の大企業優遇の歴 史はこんなところからなのかと思った。
それで、人事権を掌握した摂関家や、貴族に下級官僚がこぞって開墾し たり奪ったりした土地を寄進します。国に税を納めても、出世につながり ませんが、摂関家に寄進すれば、官位が上がって、実入りのいい土地に 赴任できる。 つまり、「低税率を選択している」 わけです。
それで、藤原氏の不仲だった後三条天皇が 短期間 院政をした時やっ たことが、内裏の改築と荘園の整理。 私物化された土地を朝廷に返せ ということですね。
大河ドラマに出て来た信西というお坊さんがしようとしたこともまさにこれ で、内裏の築造(天皇の権威を象徴)と、荘園の整理だったわけです。 摂 関家の力をそいで、国(朝廷)に税を取り戻そうとしたわけです。
そのために、今まで 都内では「威嚇して従わせるだけ」 だった武士を
「戦闘させて貴族をおとなしくさせた」 摂関家の私兵であった清和源氏 よりも 平家を重用したのも、そのためだった。
ドラマでは、イヤらしく 信西さんに 「広く薄く税を取り、民が楽になった」
と、言わせていましたが、実はその前に、私物化されていた荘園をかなり 国に取り返したことで 「広く薄く」が実現したわけです。
現在で言えば、官僚が私物化している特別会計を国民に取り返し、
広く薄く税を取るにしないといけないわけですね。
摂関家から人事権を取り上げた
で、後白河天皇側が勝ち、崇徳上皇側に 摂関家の頼長がいたことで、
信西は、すぐさま、その兄で養父となっている藤原忠通に、「藤原の氏長 者を授ける」と わざわざ伝えます。 藤原氏としては朝廷に関係なく藤 原氏だけで決めていた氏長者の座を 天皇からの任命という形にしてしまいます。 これは、藤原氏(摂関家)にとっては屈辱的なことです。
摂関家の力は、朝廷の官僚制度を私物化して人事権を握ることが源泉 なのですからその力の元が、天皇に握られることになります。
現在で言えば、官僚が代々引き継いでいる「認証官」を、国会同意人事 にしちゃうぐらいすごいことです。
平治の乱で、信西が死んでしまったために 元に戻ってしまい五摂家とし てエンエンと続いて、明治維新を迎えるわけです。
官僚の手法というのは、この時代からあんまり変わっていないんですね。
清盛が本当に武士の世を作りたいと思っていたなら保元の乱のときに
源義朝と一緒に、後白河天皇も、崇徳上皇も幽閉して、新しい天皇を立 てちゃえば良かったのです。 あのドラマでは「武士の世を作る」なんて言 っていますが、実際では、朝廷でもっと上の官位が欲しかっただけなんで す。
全く、西松事件の時に、国会議員が団結して、あの起訴を辞めさせてい れば、検察に縛られることもなかったのに、
「自民党には及ばない」
なんていう言葉に踊らされて保身にまわった議員たちのようです。
この2冊の本については、とても書ききれませんが、何度読んでも、発見 があります。
最後に。。
続日本紀という宣命体の本には、「天皇がこうおしゃった」という肉声が
書かれているそうです。 聖武天皇と光明皇后の娘で 天皇になった
孝謙天皇の言葉はとても長いそうです。それは、なぜか?
彼女は、吉備真備にしっかり国づくりなどを学んだキャリアウーマンであ り、自分の言うことに自信を持ってはいる。 しかし、周囲の臣下たちには は、今までと違うので納得させるのは難しいだろう。だから、まず、自分を これでいいんだと 納得させながら、周囲を納得させるので、説明が長く なる。
というようなことを橋本さんは書いています。
全く、泣けてきます。。
御来訪ありがとうございました。